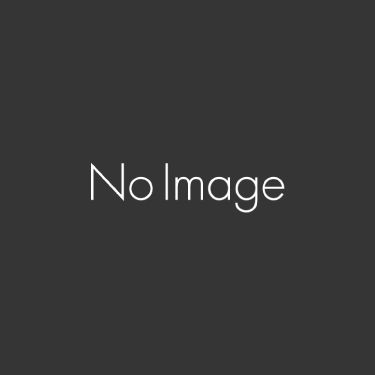※ネタバレを含みますのでご注意ください。
映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を観るときに知っていたらもっと面白くなる雑学・豆知識・考察をまとめました。
特に2回目を観るなら知っておくとより楽しめること間違いなしです!
猗窩座は過去・人間時代を無意識に反映している
猗窩座は、人間だった頃の記憶を無くしていますが、無意識だと思いますが、人間時代の様々なことを鬼となった自分自身に反映させています。
女を食べない理由
ほとんどの鬼は我を忘れて夫や自分の子供でさえ食べてしまいますが、猗窩座は恋雪への想いのためか、女性を絶対に食べません。
このことからも、女性ばかりを食べている上弦の弐・童磨のことが嫌いです。
弱者が嫌いな理由
人間時代は、病気の父親や恋雪などの弱者に対して、罪を犯してまで薬代を稼ぎ、甲斐甲斐しく看病をすることも何とも思っておらず、弱者であることはその人のせいではないし仕方のないことだと思っていました。
しかし、慶蔵と恋雪が毒殺されたことで、弱者は正々堂々と戦わずに卑怯であるということが結びついてしまい、弱者は卑怯→弱者は嫌いという極端な考えになったと思われます。
正確には弱者ではなく卑怯者が許せないのですが、記憶を無くし、強さを求めるあまりに弱者が嫌いとなったのでしょう。
炭治郎に卑怯者と呼ばれたときは、心の底から嫌悪したと思います。
炭治郎は「透き通る世界」で、猗窩座を背後から不意打ちすることができましたが、わざわざ声をかけて気づかせてから首を切りました。
これで分かりやすく正々堂々ということや炭治郎の性格を表現しているのだと思いますが、もし炭治郎が不意打ちしていたとしても、戦いの最中に実力で不意打ちされたのだから卑怯だとは思わなかったと思います。
そもそも鬼の回復力も、相手が2対1で戦っていることも卑怯とは思っていません。
猗窩座は戦わずに毒を盛るようなことを卑怯だと思っているはずです。
とはいえ、背後からの不意打ちではなく正面から正々堂々と勝負して負けたことで、何の曇りもなく完敗だと認められたのだと思います。
猗窩座の技・血気術「破壊殺」
猗窩座は人間のときに修得した武術「素流」を元に、血気術「破壊殺」として技を昇華させています。
「破壊殺」という名前の由来は、五大凶方のひとつで、その年の十二支がいる対面側の方角を表し、あらゆるものすべてが破壊されるとされています。
猗窩座が使用した「破壊殺」は以下の10種類。
- 羅針
- 空式
- 乱式
- 滅式
- 脚式 冠先割(かむろさきわり)
- 脚式 流閃群光(りゅうせんぐんこう)
- 脚式 飛遊星千輪(ひゆうせいせんりん)
- 砕式 万葉閃柳(まんようせんやなぎ)
- 鬼芯八重芯(きしんやえしん)
- 終式 青銀乱残光(あおぎんらんざんこう)
相手の闘気を感知し、相手の位置を把握し、攻撃を予測する術式展開「破壊殺・羅針」の構えは、「素流」の構えで(単行本の設定こぼれ話に書かれています)、当然ながら師匠の慶蔵の構えとも完全に一致しています。
さらに、このとき地面に現れる雪の結晶のような模様は、恋雪が愛用していた髪飾りのデザインがモチーフとなっており(単行本の設定こぼれ話に書かれています)、恋雪のことは覚えていませんが、無意識に恋雪への想いが現れていると思われます。
敵の位置を把握する索敵能力が発現したのは、慶蔵と恋雪が毒殺されたときに敵に気づくことができなかったことからかもしれませんね。
そして、技とその技名は、恋雪と見た思い出の花火がモチーフになっています(単行本の設定こぼれ話に書かれています)。
公式ファンブック「鬼殺隊見聞録・弐」にも、技の名前や形は人間の頃の思い出が反映されると書かれています。
おおよそ以下のような花火が名前の由来と思われます。
- 脚式 冠先割 → 冠先割
(先割は消える直前にパリパリッと乾いた音を発する花火を表す) - 脚式 流閃群光 → 閃光万雷
(群光は多くの光が同時に広がる様子を表す) - 脚式 飛遊星千輪 → 飛遊星・千輪菊
- 砕式 万葉閃柳 → 柳
- 鬼芯八重芯 → 八重芯菊
(八重芯は芯の構造を表し、中央に二重の芯部を持ち、計三重の花が開く花火のこと) - 終式 青銀乱残光 → 青銀乱・残光
花火は、打ち上げられて上昇中の様子 → 芯部 → 開花後の変化の様子 → 玉の種類 → 消え際・末端の変化の様子を順番に並べて名前が付けられます。
映画の第2弾キービジュアルの猗窩座の瞳には花火が映っています。
猗窩座の中に狛治だったときの思い出が残っていることを表しているようですね。
【7月18日(金)公開】
— 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) June 28, 2025
劇場版「鬼滅の刃」無限城編
第一章 猗窩座再来
第2弾キービジュアルを公開しました。
▼本予告はこちらhttps://t.co/qlPaqJvBEZ
宴の時間だhttps://t.co/2KjmHDTvTr#鬼滅の刃 #無限城編 pic.twitter.com/tq7Tjq1S0k
羽織(服)の色と模様(文字)
猗窩座の全身にある幾何学的な文様は、人間時代に罪人の証として両腕に入れられた6本の墨が鬼の紋様と混ざり合い、全身に広がったものと考えられます(単行本の設定こぼれ話に書かれています)。
剣術道場の67名を殺害し、さらに罪を重ねたからかもしれません。
それと同じような模様が羽織の背中部分にも描かれているのですが、逆さにすると「孤峯の雪」という「香道」で香りをあてるゲーム「三種香」の答えを表す3本線の図(記号)になっているのです。
孤峯とは、周りに高い山がなく、ただ一つそびえる峰のこと。
「孤峯の雪」はまさに狛治にとっての恋雪のことではないでしょうか。
羽織の色や帯の色も恋雪の着物の色を反映していると思われます。
こほうのゆき?調べたら香道の種類らしく画像を見比べてみたら……ギャー❗
— 倉岸谷 (@s1205Y5gH4N) July 25, 2025
あかざさん?おまっ、背中にっ、嫁の名前っ、えっ、罪人の証の入墨が全身に纏いつつも恋雪ちゃんの名前も刻んでいたの?え?しかも背中に直接じゃなく服に刻んでるあたり然り気無さを感じて?え、ちょっ待っ情緒が https://t.co/lABDafs6dM pic.twitter.com/8IuIpvljcK
強者の名前を聞き、鬼に勧誘する理由
猗窩座は戦いの中で強さを認めた相手の名前をしつこいほど聞きます。
そして、初対面でも馴れ馴れしく下の名前で呼び、「鬼にならないか?」としつこく勧誘します。
表面上は、強い者に対する尊敬やお気に入りの気持ちから純粋に名前を知りたい、一緒に鍛錬して強くなりたい、ずっと戦っていたいと思っているように見えます。
これは人間時代、師匠の慶蔵との思い出が元になっているのではないかと思います。
慶蔵は狛治に出会い、連れて帰ったときに何度もしつこく名前を聞きますが、狛治はなかなか答えず、慶蔵は恋雪に狛治の名前を聞いておいてくれと頼みました。
このときの思い出や、自分を受け入れてくれた慶蔵の性質が猗窩座に影響を与えていると考えられます。
猗窩座は、名前を聞くことは相手のことを受け入れている証なのだと思っているのではないでしょうか。
そして、鬼に勧誘するのも、相手を受け入れているからであり、慶蔵が自分を受け入れてくれたことが影響しているのではないでしょうか。
猗窩座の人懐っこさは慶蔵譲りだと思います。
ただ本当は、自暴自棄になり暴力を振るっていた狛治を慶蔵が改心させたように、猗窩座も鬼から改心させてくれる(鬼の自分を倒してくれる)慶蔵のような強者を求めていたのかもしれません。
慶蔵と恋雪が毒殺された経緯
慶蔵と恋雪が毒殺された経緯については原作漫画でも描かれず、単行本の空きページに文章で書かれています。
長くなるために本編に入れられなかったとのことです。
今回の劇場版アニメでも描かれませんでした。
今後、テレビアニメ版が作られることがあれば、このエピソードもぜひアニメ化してほしいですね。
慶蔵の道場の隣の剣術道場には、恋雪と同じ年頃の道場の跡取り息子がいました。
彼は恋雪のことが好きでしたが、乱暴で横柄な性格で、具合の悪い恋雪を無理やり外に連れ出した挙げ句、喘息の発作を起こして苦しむ恋雪を見て怖くなり、放置して逃げました。
狛治が見つけなければ、恋雪は死んでいたところでした。
怒った慶蔵は隣の道場と試合を行い、慶蔵が後に控えていましたが、狛治が一人で9人を倒し、今後、素流道場と恋雪に関わらないように約束させました。
怒って取り乱した跡取り息子は真剣で狛治に斬りかかりますが、狛治は振り下ろされる刃を側面から拳で打ち叩き、真っ二つに折りました。
それは狛治が一番得意とする「鈴割り」という技で、原作漫画や劇場版アニメでも猗窩座が義勇に対して使用しました。
その技のあまりの美しさに隣の道場主は感動し、負けを認めて跡取り息子の無礼を詫び、素流道場への嫌がらせをやめました。
数年後、隣の道場主が亡くなり、狛治と恋雪の結婚の話を聞きつけた跡取り息子は、門下生の焚き付ける声もあり、戦っても勝てないため素流道場の井戸に毒を入れました。
向かいに住んでいるおばあさんが素流道場から出ていく跡取り息子と門下生を目撃していました。
毒を飲んでしまった後、慶蔵は恋雪を抱えて、医師の家まで血を吐きながら走りましたが、恋雪はすでに亡くなっており、慶蔵は亡くなるまで長い時間苦しみました。
その後、狛治が剣術道場を襲撃した際に、この跡取り息子も殺害しています。
獪岳は悲鳴嶼行冥の寺にいた子供
善逸の兄弟子であり、鬼となった獪岳ですが、子供の頃は岩柱・悲鳴嶼行冥の寺で暮らしていました。
そして、自身が助かるために寺に鬼を招き入れた子供こそが獪岳だったのです。
このことは原作、アニメでも直接語られてはいませんが、見た目で気づく人はいたでしょう。
(単行本の設定こぼれ話に書かれています)
原作にないアニメだけのオリジナルシーン・描写
原作では描かれていない劇場版アニメだけのオリジナルのシーンや描写がたくさんあります。
ここで挙げる以外にも細かいシーンや描写がたくさんありますのでぜひ意識して見てみてください。
また、こういうシーンを追加してほしかったということもそれぞれにあると思います。
無限城の描写
今作の見どころのひとつとして、無限に広がり変化していく無限城の表現、描写があります。
漫画では表現できない、アニメならではのシーンですよね。
最初の計算では3DCGで描画(レンダリング)するのに、第一章だけで3年半(3部作で10年)かかると算定されたそうです。
それをスタッフたちの様々な努力により、大幅に短縮し、現実的な時間内に完成させたのです。
この無限城の圧倒的表現により、戦闘アクションを始め、様々なシーンがより良いものになったといえます。
特に、お館様の後継者である産屋敷輝利哉が指揮を執り、愈史郎と鎹鴉から得た情報で無限城の図面を描くシーンは、重要な役割だったことがより伝わるものになったと思います。
胡蝶しのぶの技「蟲の呼吸 五つ目の舞」とエフェクト、舌打ち
蟲柱・胡蝶しのぶの蟲の呼吸は、水の呼吸から派生した花の呼吸からさらに派生させ、自ら編み出した独自の呼吸です。
独自の呼吸のため、他の呼吸のように型がなく、「〇〇ノ型」ではなく「〇〇ノ舞」と呼んでいます。
(ちなみに伊之助が独自に編み出した獣の呼吸も同じく型がなく、「〇〇ノ牙」と呼んでいます)
原作で描かれた蟲の呼吸の技は4つ。
- 蜂牙ノ舞 真靡き(ほうがのまい まなびき)
- 蜻蛉ノ舞 複眼六角(せいれいのまい ふくがんろっかく)
- 蜈蚣ノ舞 百足蛇腹(ごこうのまい ひゃくそくじゃばら)
- 蝶ノ舞 戯れ(ちょうのまい たわむれ)
今作のアニメでは、原作漫画には登場しなかった蟲の呼吸の五つ目の舞(技)が描かれました。
それが、蟲の呼吸・虻咬ノ舞 切裂の誘い(もうかのまい せっさくのさそい)です。
漢字表記は、劇場公開から3日後の7月22日に発売された『劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来 ノベライズ』で明らかになっています。
蟲の呼吸のエフェクトは漫画では描かれていませんが、アニメでは描かれていました。
蜂牙ノ舞 真靡きはハチ、蜻蛉ノ舞 複眼六角はトンボ、蜈蚣ノ舞 百足蛇腹はムカデの迫力ある画でした。
『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』でも、煉獄さんの原作未登場の型、炎の呼吸・参ノ型 気炎万象(きえんばんしょう)がアニメオリジナルで描かれました。
『無限城編』第二章、第三章でも、柱たちのアニメ初登場の型が描かれるかもしれません!
また、童磨に対して舌打ちするシーンもアニメオリジナルで、SNSでも話題になっており、とても好評ですね!
胡蝶しのぶ役の早見沙織さんと童磨役の宮野真守さんのお二人の演技が素晴らしく、最高の戦いになったと思います。
村田さんの水の呼吸の型
愈史郎と村田さんたちが善逸の手当てをしているとき、襲ってきた鬼に対して村田さんが「水の呼吸 弐の型 水車」を使って鬼を倒すシーンが描かれました。
しかも、僅かにですが水のエフェクトが見えていました(水流は見えなかった)。
原作漫画には、村田さんについて「使っているのは水の呼吸なのですが、薄すぎて水が見えません」と書かれていました。
炭治郎たちが使う呼吸や技のときに見える水や炎などは実際に出ているのではなく、見ている人がそう感じる、そう見えるというだけで、強さと比例しているようです。
つまり、村田さんの技が水のエフェクトが視覚できるほどに強くなったということです。
実際に下弦の鬼ほどの力を持たされた鬼たちを次々と倒しています。
アニメ『柱稽古編』でも隊士たちの奮闘が描かれましたが、劇場版『無限城編』では、村田さん始め、隊士たちの活躍、柱稽古を経て強くなった姿が描かれていました。
産屋敷輝利哉の指揮の下、無限城の図面を繋げていく鬼殺隊の隠(かくし)たちの活躍もそうですが、最前線で戦う柱や炭治郎たちだけでなく、鬼殺隊全員で戦っていることに重きを置いていると感じました。
胡蝶しのぶのハンドサイン(指文字)の意味
※第二章のネタバレを含みますのでご注意ください。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第二章で描かれると思われますが、胡蝶しのぶがカナヲに送ったハンドサイン(指文字・手話)の意味は「息を吸うな」です。
つまり、童磨の血気術である冷気を吸わないようにと伝えるためのサインでした。
童磨は、自身の血を凍らせて微細な氷の霧を発生させ、それを吸った相手の感覚器や呼吸器系を冒します。
吸っただけで肺が凍りついて壊死してしまう初見殺しの攻撃のため、これだけは伝えなければと思ったのでしょう。
たとえ知っていたとしても呼吸が基礎となる鬼殺隊の戦い方を大幅に制限させる、対鬼殺隊の技ともいえる血気術ですね。
私は最初に漫画を読んだときは、「作戦通りに」ということを伝えたのだと勘違いしていました。
『ジョジョの奇妙な冒険』3部で、花京院がDIOの時を止める能力を伝えるためにエメラルドスプラッシュで時計台を破壊したことを思い出しました。